第七話 黄金の雷(10)
ミカエラたちと別れた後、ディエゴは、トゥパク・アマルの囚われたことも、本陣での敗戦も、まだ何も知らぬ、ラ・プラタ副王領のアンドレスとアパサの元に、インカ軍本隊の状況を伝えるため使者を放った。
いかに早馬の使者とは言え、隣国までの道程は遠く、使者がアンドレスたちの元に到達するまでには何日間もの期間を要するであろう。
ディエゴは迅速にインカ軍本隊を建て直すと、ビルカパサと共に大軍を率いてトゥパク・アマル奪還のため、すぐさま踵を返してスペイン軍との対決に向かった。
アンドレスの朋友ロレンソも、18歳という彼自身の年齢と同様に、若く気鋭の軍勢を率いてディエゴらと共に戦闘に向かう。
これらトゥパク・アマルの救出に向かった軍団の中には、まだ致命的な負傷をしていない多くの義勇兵たちが加わっていた。
今度こそ、いよいよ生き残る保障の無い戦いであり、覚悟を決めた有志の義勇兵たちが募られ参戦した。
その中には、あの黒人青年ジェロニモの姿もあった。
一方、マルセラは連隊長である叔父のビルカパサの隊を離れ、分遣隊を編成し、負傷した兵たちを保護して避難をさせながら、まだインカ側の勢いがあるラ・プラタ副王領に向かった。
目指すは、アンドレスの陣営である。
マルセラ率いる義勇兵たちの中にはコイユールも混ざっており、彼女も負傷兵の世話をしながら避難を助け、マルセラを背後から支えた。
しかしながら、この厳しい戦況の中、負傷兵を抱えながらの隣国への道程の険しさは、到底、計り知れぬものである。

そうした中、トゥパク・アマルの妻ミカエラ及び彼らの息子たちは、ディエゴの提案通り二手に別れ、敵に目立たぬよう軍団を離れて、やはり、アンドレスの陣営を目指していた。
ミカエラと長男イポーリト、そして末子フェルナンドは、インカ軍の参謀でもある豪腕オルティゴーサ及び数十名の彼の精鋭の兵たちに堅く守られながら、敵の目をかすめるため、アンデス山脈の奥深い獣道をルートに取りながら進んでいった。
他方、次男マリアノは、トゥパク・アマルが全幅の信頼を置いていた壮年の賢者ベルムデスと、そして、影武者のごとく付き従う敏腕の護衛兵たちと共に、貧しい平民の姿に扮し、何も不審なところは無いという素振りで、敢えて堂々と街道沿いを通っていった。
こうして、それぞれの者たちが、命懸けの新たな道を歩みはじめたのである。
ところで、後世の歴史家たちの記録によれば、この時のインカ族の人々は、「(約200年前の)ピサロのインカ帝国征服時とは多いに異なり、首領インカ(註:インカ皇帝=トゥパク・アマル)を失っても、絶望することはなかった」という。
歴史家たちは、そうした彼らの心理を、「(註:最初のインカ帝国侵略時は)初めて白人とぶつかって、何ら精神的な準備が無かったのに対して、トゥパク・アマルに此度の戦いの意義を繰り返し教えられ、不退転の意志で戦っているのとの違いである」と、分析している。
こうした記述に表されている通り、さる4月6日、トゥパク・アマルが裏切りのために捕虜となって以来、ディエゴらに率いられたインカ側の軍団は、絶え間なく猛烈な戦いをスペイン側に挑み続けることになる。
トゥパク・アマル奪還を賭けたランギ村周辺での最初の戦闘は敗北したが、次に行われたピサク川の対岸における決戦では、インカ側が、まだその力の残っていることをスペイン側に見せつける戦果を上げた。
この時は惜しくもトゥパク・アマル奪還までには至らなかったが、それでも、ディエゴら側近たちの指揮の元、彼らはまだ戦えるという手応えを得て、「トゥパク・アマル様を救出すべく、クスコまで進撃だ!!」とばかりに勢いづいた。

スペイン側としては、総指揮官トゥパク・アマルを捕えたにもかかわらず、戦火が衰えるどころか、むしろ激しさを増すインカ軍の戦闘ぶりを放置できず、ついにスペイン軍総司令官バリェ将軍が、直々に「インカ軍残党の始末」に乗り出すことになる。
かくして、ディエゴ及びビルカパサの軍、そして、ロレンソの軍を中心とるすインカ軍の主力部隊は、トゥパク・アマル奪還を誓い、彼が連れ去られたクスコ目指して進軍を続け、途上のコンドルクヨの高地で、バリェ将軍率いる重装備のスペイン軍と激突した。
トゥパク・アマル奪還を賭けて、残されたインカ軍がどれほど凄まじい死闘を繰り広げたかは、後世の歴史家たちが叙述しているごとくであり、その一例として、ここでは創作よりも、むしろ真実をありのままにご紹介したい。
以下は、ペルーの歴史家オドリオソーラの手のより残されている、当時のスペイン側から見たインカ軍の様子である。
なお、ここではビルカパサの軍に焦点を当てて叙述されている。
『バリェ司令官は、ペルー南部の諸郡に蟠踞(ばんきょ)する反乱軍の残党の討伐に向かった。
コンドルクヨの高地に、名将ビルカパサの率いるインディオの軍がいるのを発見した。
バリェ軍の兵はビルカパサ軍に向かって、「もし山から降りてきてスペイン国王に服従を誓えば、許してやる」と大声で降伏を勧めたが、彼らは、「これからクスコへ『インカ(註:インカ皇帝=トゥパク・アマル)』を救いに行くのだ、お前たちは勝手にどこへでも行くがよい」と、応えた。
結果、両軍は激突して、熱戦が続いた。
わが方(註:スペイン側)も多くの死傷者を出した。
我らの征服者(註:16世紀にインカ帝国を侵略したピサロたちのこと)の時のインディオの臆病さ、単純さとは違うことを示すために、二つの例を引いてみよう。
胸に槍を突き刺された一人のインディオは、獰猛にも自分の手でそれを引き抜くと、逃げる敵をその槍で刺し殺そうと追いかけたが、ついに息が切れて倒れた。
他の一人は目を槍で突かれたが、ひるまずに相手を追いかけた。
もし途中で殺されなければ、この片目の負傷兵は、首尾よく仇を討ったことであろう』
しかしながら、このコンドルクヨの戦いも、スペイン側の火砲の威力には抗(あらが)えず、結果的にはインカ側の敗戦に終わる。
だが、数々の熾烈な戦闘を経てもなお、ディエゴ、ビルカパサ、そして、ロレンソら、インカ側の将たちは執念を燃やすがごとくに、まだ生き延びていた。
また、義勇兵たちも、甚大な被害を蒙りながらも強靭な生命力を見せ、容易に全滅することはなかった。
彼らはトゥパク・アマル奪還を念じて心をひとつに合わせ、どれほど敵に踏みつけられようとも立ち上がり、クスコ目指して捨て身の進軍を続けていった。
一方、ディエゴらが壮絶な死闘を展開している頃、インカ軍参謀オルティゴーサに守られながら山岳地帯の獣道をラ・プラタ副王領目指して進んでいたトゥパク・アマルの妻ミカエラ及び、長男イポーリト、そして末子フェルナンドらは、どのようになっていたであろうか。
なんと、ミカエラたちには、はやくも、残酷な運命の魔手が及んでいたのである。
非情にも、彼女たちは、急峻な山岳地帯の一角で、執拗に追ってきたスペイン兵たちの襲撃を受けていた。
そこはアンデス山脈の懐深い前人未到の地であり、決して容易に発見されるような場所ではなかった。
それにもかかわらず、彼らが敵の追っ手にその軌跡を掴まれてしまった背景には、ミカエラが管理していた多額の軍資金を狙ったインカ側の者の裏切り行為があった。
トゥパク・アマルが反乱準備を進めていた頃には、あれほどの長期に渡る準備期間にもかかわらず、決して裏切り行為など起こりえなかったにもかかわらず、ここにきて裏切りが連続したことは、インカ側の命運の尽きてきたことの表れなのか、あるいは、いよいよ戦況が苦しくなってきたことで、人々の心に、ほころびが生じてきたことの証(あかし)なのか…――いずれにしろ、夫トゥパク・アマルと同様、ミカエラ自身もまた、味方の裏切りによって、今、窮地に立たされていたのだった。
トゥパク・アマルと同じように、私利私欲のことなど全く考えず、インカの天地とその民のために全身全霊を捧げてきたミカエラにとって、あまりに悲愴で、理不尽な、運命の所業ではなかろうか。
だが、実際に、彼女らは、多数の銃器を携えた数十名の敵兵たちの奇襲を受けていた。
ミカエラたちを護衛していた参謀オルティゴーサは、インカ軍本隊の中でも右に並ぶものの無きほどの豪腕の持ち主であり、彼と共に護衛に当たっている兵たちも、選り抜きの部隊であった。
結果、この深山の秘境の地でも、激しい死闘が繰り広げられた。
しかしながら、時間の経過と共に、ここでもスペイン側の火器の威力は、インカ側を着実に圧倒していく。
しかも、此度のように苦心惨憺(さんたん)たる思いをさせられた反乱をニ度と起こさせまいと、意地でもトゥパク・アマルの息子やその妻を捕えて、インカ(皇帝)一族を根絶やしにせんとする敵側の執念は、それはもう、凄まじきものであった。
その復讐心の炎に焼け出されるがごとくに、さしものオルティゴーサも、そして、彼の兵たちも、次第に追い詰められていく。
オルティゴーサが拳銃と剣を振るいながらも、敵の銃弾をかわすために大木の陰に寄った瞬間をとらえ、専門兵たちを凌ぐほどに雄々しく華麗な剣裁きで長剣を振るっていたミカエラが、敏捷な足取りで彼の傍に近寄った。
 よもや、ゆるぎなき覚悟を決めたミカエラの表情から、オルティゴーサは、彼女が何を言い出すのかを瞬時に悟った。
よもや、ゆるぎなき覚悟を決めたミカエラの表情から、オルティゴーサは、彼女が何を言い出すのかを瞬時に悟った。
「ミカエラ様……!」
ミカエラは、決然と頷き、非常に険しくも凛々しい眼差しで、きっぱりと言う。
「もはや、敵の手に落ち、辱めを受けて死ぬよりは、自らの手で命を絶ちます。
オルティゴーサ殿、援護を!!」
ミカエラの言葉に、オルティゴーサは愕然と目を見張る。
「――!!
しかし、ご子息様たちは…!!」
「息子たちも、わたくしと共に参ります」
「ミカエラ様!!
トゥパク・アマル様は、囚われたとはいえ、まだご存命なのでございます!
あなた様が、先立たれなどしたら、どれほど御失意なされることか!!
それに、ご子息様とて…――そのようなことをすれば、皇帝陛下のお血筋が…――!」
ミカエラは、毅然とした眼差しで、真正面からオルティゴーサを見つめた。
この期に及んでも、なお、ミカエラの彫像のような目元は、女神のごとくに麗しい。

彼女は、噛み含めるように言う。
「オルティゴーサ殿。
自ら命を絶たねば、今、ここで、わたくしも息子たちも捕えられてしまいましょう。
そうなれば、敵方の役人どもに、いかなる目に合わされるかは自明。
仮に、この後、味方の軍が勝機を掴もうとも、囚われた後では、敵方は、逆に、捕えたインカ一族の処刑を急ぐはずです。
このままでは、夫もわたくしも…息子たちとて、民の面前に晒され、あの処刑台に送らて死すのです。
侵略後、これまで反乱を試みてきた歴代のインカ皇帝たちが、どれほどの無残な刑に処せられてきたか存じておりましょう?
そのような形で、トゥパクの…――インカ皇帝の血筋が絶たれていくさまを、インカの民に見せられましょうか。
それこそ、あまりに深い絶望と屈辱感を、民の心に刻みつけることになりましょう。
そのようなことになれば、此度の戦(いくさ)によって、やっと甦りかけていたインカの民の誇りも復権意識をも、再び根こそぎ刈り取ることにもなりかねまい。
そのような事態は、決して招いてはならぬこと。
もはや、選択肢は無いのです。
それに、天運あれば、マリアノが生き延びてくれましょう。
オルティゴーサ殿、傍近くで夫を長く助けてきたそなたなら、わたくしの言うことの意味をわかってくれますね?」
ミカエラは決然としながらも、衝撃に貫かれている相手を諭し勇気付けさえするような口調でそう述べると、完全に覚悟を固めた面差しでオルティゴーサを見据えた。
「オルティゴーサ殿、時間がありません。
そなたには、わたくしたちが成し遂げられるよう、援護を頼みたいのです。
さあ、もう少し奥まったところに。
息子たちには、既に話してあります」
「ミカエラ様…――!!」
オルティゴーサの声が詰まる。
「申し訳ございません!!
わたしが、しかとお守りしきれず…!!」
彼は、その厳(いかめ)しい肩をわななかせながら、深く頭を下げた。
「何を言うのです。
オルティゴーサ殿、そなたは今まで本当によくやってくれました。
参謀としてのそなたの采配無くして、インカ軍がここまで奮戦することなど、ありえなかったことでありましょう。
このような結果になって、謝らねばならぬのは、夫やわたくしの方なのです」
オルティゴーサは、もはや声も出ぬまま、まともにミカエラを見ることもできず、だが、彼もまた、覚悟を決めた足取りで、ミカエラを、そして、少し奥地で待っていたトゥパク・アマルの息子たちを、さらに山間部の奥地まで導いていく。
そうしながら、彼は、俊敏に、戦線に視線を走らせる。
敵兵たちは、オルティゴーサの部下たちとの戦闘に意識を奪われており、奥地へ入っていく彼らの姿には気付いていないと見て取れた。

ミカエラは大木と野草で囲まれた一角に自決する場所を定めると、オルティゴーサに目で頷き、合図を送る。
オルティゴーサは、悲壮な面持ちながらも厳然たる眼差しで、瞬間、その場に巨体を跪き、ミカエラたちに向かって深々と礼を払った。
ミカエラも、息子たちも、彼に深い礼を払い返す。
オルティゴーサは、もう一度、深く身を屈めて最後の礼を払うと、鋭い眼で立ち上がった。
そして、敵襲に備えてミカエラたちに背を向け、彼女たちを固く守護するように、その場所の前に豪然と仁王立ちになった。
決して、ここに敵は通さぬ!!…――鬼気迫る覇気が、今、彼の全身から激しく放たれる。
オルティゴーサの様子を見届けると、ミカエラはイポーリトとフェルナンドの前に跪き、共に死路へと旅立とうとしている愛しい息子たちの唇に、優しく最後のキスをした。
それから、二人を同時に力強く抱き寄せる。
長男のイポーリトは完全に事態の成り行きを察し、12歳にはとても見えぬ、もはや大人のごとくの決然とした表情で、逆に、母であるミカエラをいたわるように抱き締め返す。
そのイポーリトからは見えぬ角度で、ミカエラの閉じた瞼には、こらえきれずに涙が滲む。
(イポーリト…――!!
本来ならば、トゥパクの後を受けてインカ皇帝となり、この地を守っていく役割を持っていたはず…――!
そして、それに相応しい人間へと、成長しつつあったというのに。
そなたたちを守り切れなかった、父と母を許しておくれ……)

一方、8歳の末子フェルナンドは、事の流れに身を委ねてはいるものの、まだ真には事態の意味を悟れず、潤んだその瞳を呆然と揺らしている。
フェルナンドのぬくもりを感じながら、その震える肩を抱き締めるミカエラの心は、この期に及んで激しく掻き乱された。
(こんなにあたたかな体から、今、この母の手で、そなたの命を……。
だけど、まだフェルナンドは、たった8歳――もしや、たとえ、囚われようとも、この幼き年齢であれば、死罪までは免れるかもしれぬ!
あのマリアノとて、もし囚われれば、10歳に達したあの子に、死罪を免れる余地はあるまい。
なれど、このフェルナンドなら……。
どのような形とて、生き延びてくれさえすれば、侵略後の数百年、幾度も絶たれそうになりながらも、ここまで永(なが)らえてきたインカ皇帝の血統を、完全には絶やさずにすむかもしれぬ。
ならば、わたくしが、今、ここで、この尊い命を絶ってよいものか……!!)
そのミカエラの一瞬の迷いに呼応するがごとくに、突如、耳を劈(つんざ)く激しい無数の銃声が、至近距離で鳴り響いた。
ハッと振り返るミカエラの視線の先で、あの仁王立ちになっていたオルティゴーサの巨体が、地に崩れるように沈んでいく。
驚愕して目を見開いたミカエラたちの瞳の中に、その全身をまるで蜂の巣のごとくに無数の銃弾に打ち抜かれ、ドウッ、と地に倒れゆくオルティゴーサの姿が映る。
ミカエラは瞬間的に、フェルナンドの目を己の手で覆った。
イポーリトも愕然として、凍りつくように、思わずその場に立ち竦んだ。
「オルティゴーサ殿!!」
ミカエラの悲痛な声が響くと同時に、彼らの前に、数十名のスペイン兵たちが立ちはだかった。
その中から、隊長らしき厳(いか)つい白人が、銃を構えながら前に進み出る。
「トゥパク・アマルの妻、ミカエラ殿と、そのご子息殿とお見受けいたす。
ご出頭願いましょう」
反射的に、ミカエラは携えていた長剣を構えた。
ほぼ同時に、イポーリトも剣を構える。
しかし、全く同じタイミングで、スペイン人のその隊長らしき男は、銃口を幼いフェルナンドにピタリと向けた。
「無駄な抵抗をされれば、ご子息のお命から頂戴いたす。
武器をお捨てください」
男は不気味に恭しい言葉遣いで、しかしながら、その声音には有無を言わさぬ凄みを宿してミカエラを見据えた。
既に、他のスペイン兵たちも、その銃口を、ミカエラたち三人に隙無く向けている。
剣を握るミカエラの指が、口惜しさで、わななくように震えた。
しかし、もはや状況を見切った彼女は、地に剣を下ろすと、そのままイポーリトにも目で合図を送る。
だが、イポーリトは、非常に険しい目つきで敵兵を睨みつけながら、己の剣を構えたまま、母と弟を守るように、一歩、前に踏み出した。
瞬時に、数十名の敵兵たちが、一斉にイポーリトに照準を合わせ、その銃を完全に構えた。
敵兵の隊長が、鋭い手つきで、部下の動きを制する。
同時に、ミカエラも、イポーリトの剣を構えた腕を掴んだ。
そして、彼女は、無言のままながらも、厳然たる眼差しでイポーリトを見つめ、首を僅かに横に振った。
だが、イポーリトは断固たる鋭利な横顔で、何故、止めるのです!!と、母の腕を振り払おうとする。
「母上…――!!」
どのみち、死を覚悟していたのです!!ならば、僕は、ここで戦って…!!――そう激しく訴えてくるイポーリトの決死の表情に、ミカエラは、再び、はっきりと首を振った。
そして、そなたの心意気はわかりました、と、イポーリトに深く瞳で頷いた後、決然としつつも、静かな声で言う。
「この者たちは、ここでは、わたくしたちを、絶対に殺しはすまい。
たとえ、そなたが敵の刃に自ら向かっていこうとも、ここでは、刺しても、撃ってもくれはすまい。
生きたまま捕えるのが、この者たちの目的。
ならば、そなたが、どれほど死するつもりで戦おうとも、今となっては、もはや生きたまま、無駄に消耗するだけです」
「母上…――!」
イポーリトは、あまりの悔しさに歪みゆく顔を隠すように、サッと深く俯(うつむ)いた。
まだ剣を構えたままの、激しい感情に貫かれ、鉄棒のように硬直したイポーリトの腕を、ミカエラが手を添えて、ゆっくり下におろさせた。
暫し、長い睫毛(まつげ)を伏せるようにして、ミカエラは、無念に肩を震わせるイポーリトを見つめていた、が、その視線を、不意に、敵の隊長めがけて、光の矢で刺し貫くように鋭く返した。
彼女の、今もブロンズの女神像のごとくに美しい目が、閃光を放つ。
――…よもや、抵抗はすまい。
捕えるならば、捕えるがよい。
これが、天運ならば、その流れに全て委ねよう。
我らの生身の肉体が、いかに拘束され、抹殺されようとも、所詮(しょせん)は、この魂を縛ることも、抹消することも、汚れたそなたたちの手では微塵(みじん)も出来はすまい。
インカの神々は、この瞬間にも、我々を、そして、インカの民を見守り、篤く庇護している。
今に、必ずや、そなたたちは、思い知る時がくるであろう…――!
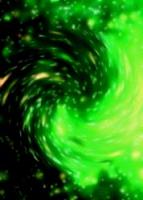
一方、彼女の鋭利な視線を受けながら、敵の隊長も、射抜くような眼光で、険しくミカエラを見据えた。
ミカエラの無言の言葉を鋭く読み抜くと、彼も、また、挑むように目を細める。
(おまえたちが、この期に及んで何を思おうが、つまるところは敗者の遠吠えにすぎぬ。
実際、囚われていくおまえたちに、何ができる?
ましてや、おまえたちを葬り去られた後の残党や民衆どもに、何ができるというのだ)
そして、ありありと皮肉を込めた声で、低く言う。
「さすがに、あのトゥパク・アマルの妻だけあって、ミカエラ殿、よくわかっておられる。
しかるべき段取りでその罪状が裁かれるまでは、おまえたちに、このようなところで死なれるわけには参らぬ。
もちろん、道中でも」
彼は鋭い手つきで周囲の兵たちに、合図を送った。
たちまち敵兵たちは彼らを捕え、ミカエラには、自害させぬために、即刻、猿轡(さるぐつわ)を噛ませた。
こうして、ついに、トゥパク・アマルの妻ミカエラも、そして、長男イポーリト、末子フェルナンドの二人の息子たちも、敵の手中に落ちたのだった。


